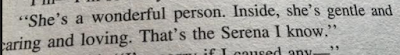高2の子が、カステラをプレゼントしてくれた!
おいしかったー。生徒のみんなで美味しく食べさせてもらいました。ありがとう!
今日は、この前のsomeの話に続いて、
小説を読んでいたら登場した英語について紹介してみよう。
英語を教えていると、
「先生が言ってたやつ、めっちゃ模試に出てたで!」って言ってもらえることがあって、
これはすごく嬉しい。と、同時に、
小説のような”ガチ”の英語で
「あ、これ、文法の授業でみんなに教えたやつだ」っていうのが出てきたりして、
これもまたハッピーだ。
「知識のための知識」じゃなくて、
本当に英語で登場することを教えてるんだなーっていう自信をもてる。
本当にささいな場面だったりするんだけど、
たとえば、これ。
息子が、お母さんに「映画行きたいんだけど」ってお願いするシーン。
"Can we watch a movie tonight?" Tim asked.
"May we watch a movie tonight," Mary corrected him.
「Can we~?」ってお願いするTImを、
お母さんのMaryが「May we」でしょ、って直している。
どちらも和訳するとほぼ一緒だけど、
mayっていうのは、"上から目線"な感じがする言葉だ。
You may use my car.
みたいにmayを使っていると、いかにも目上の人が許可を与えてやっている、って感じがする。
そのせいで、
自分から「~してもいいですか?」って尋ねるときも、
Can I~? よりも May I ~?のほうが、丁寧っていうか、へりくだってる感じがする。
「許可していただけませんか?」みたいなニュアンスだ。
日本語だと、「映画行ってええ?」って言う息子に、「行ってもいいですか、でしょ!」とお母さんがたしなめている感じに似ている。
これもおもしろい。
Anneという女性のもとに匿名の手紙が届き続けるんだけど、
それが誰から送られているのかを調査した探偵会社の人のセリフ。
"They are being sent by a Mrs Ruby Flowers."
"Who? Why?" said Anne, impatient for answers she did not want to hear.
人の名前に「a」がついている。
普通はそんなことしないんだけど、
そこにあえて「a」がついていると、まるで a personとか、a ladyとか、
そういう感じがしてくる。つまり、人名というより、「ある人」とか「ある女性」とかという方に重点がいくイメージ。
「a Mrs Ruby Flowers」なら、「Ruby Flowers」という名前そのものに注目が行くというより、
「Ruby Flowersっていう、ある人物」から手紙が届いているようですよ、という感じ。
逆に、theがついたりもする。
精神的にまいってしまって、暴言ばかり吐く奥さんについて、
旦那さんが擁護するシーン。
"She's a wonderful person. Inside, she's gentle and caring and loving. That's the Serena I know."
Serenaという人名にtheがついている。
「本当は内面ではgentleで、caringで、lovingで・・・ それこそが、私の知ってるSerenaだ」
という感じが出ている。
今は調子が悪いだけで、「私が知ってる本当のSerena」、「the Serena I know」は、
それとは違うんだよという雰囲気が、このtheから伝わってくる。
こういうのは、全部、塾で使ってる文法の本に載ってる。
文法をやっていると、どうしても「細かいなー」とか「単調すぎてつまらん」とか思っちゃいがちなんだけど、
いざ英語に触れているときにその力が発揮されると、やっぱり嬉しくなる。
高校生の場合は、文法っていうと、大概は4択の穴埋め問題という感じになる(し、それは、そういうテストで文法力が計測される以上、別に悪くもなんともない)んだけど、
たまには英語の文を読みながら「あっ、これ前にやったやつだ!」と発見したりして楽しんでほしいなーと思う。よし。